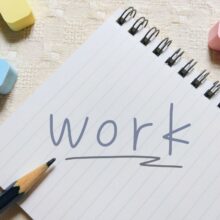確定拠出年金推進協会 代表理事の藤田雅彦です。
前回は「ベンチマーク」について、語源からひも解いてみました。
今回は、投資の世界で何故「ベンチマーク」が必要なのかを考えてみたいと思います。
投資信託を例にとってご説明します。
投資信託を例にとって
ベンチマークは、運用の企画、運用の評価のそれぞれの段階で使用されます。運用は、実質的に委託する側、実質的に運用を受託する側が存在します。投資信託の場合は、投資家(法人・個人)が委託する側、運用会社(アセット・マネジメント会社、又は、その再委託先)が受託する側です。
運用の企画段階
国内株式に投資する投資信託でTOPIXをベンチマークとしたアクティブファンドを想像してください。投資家サイドは、「なるほど、TOPIXをベンチマークとしているのなら、その投資信託だけ、大きく下落することはないだろう。」と想像します。一方で、「TOPIXを上回る成績を上げるためにどのようなリサーチを行うのだろう」と想像して、目論見書を読み進めていきます。バリュー投資なのかグロース投資なのか?はたまた独自の分析手法があるのならどのようなものなのか?と想像が膨らみます。
運用サイドは、TOPIXの過去のリスク・リターンのデータを見ることができるので、TOPIXに「少し勝って、大きく負けることのない」銘柄を探していくことになります。
ベンチマークがあることで、「期待値の集約」が図られることになります。
運用の評価段階
投資家は、月次レポートなどをみて、投資したファンドがベンチマークを上回っているかを確認できます。もし、大きく下回ることがあれば、見切りをつけて売却するかもしれません。相場が悪いときであっても、ベンチマークを上回っていれば、期待を込めて継続保有することでしょう。
一方、運用担当者は、ベンチマークを下回る運用成果しか出せない場合は、投資家から見放され純資産額も減少することが予想されます。また、上司の評価も厳しくなりますので、自分のボーナスの数字が気になってきます。ベンチマークを上回る成績を継続的に上げているなら、「カリスマ・ファンドマネージャー」と称されて、ボーナスの数字も大きくなる期待が膨らみます。
このように、ベンチマークがあることで、投資家や上司からの評価も簡単にできることになります。
基準(ベンチマーク)を設定することは、運用の世界においては、とても重要であることがお分かりいただけたと思います。ちなみに、ベンチマークを設定していないファンドも多くあります。そもそもベンチマークとなるインデックスがなかったり、特殊なテーマのファンドでベンチマークを設定することが困難だったりするからです。